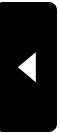【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ②勉強方法(課目Ⅱの熱力学)
2018年08月12日
これらの記事は
専門外の私がエネルギー管理士を一発合格した体験記です
記事は①~⑦まであり、
①受験背景と試験概要
②勉強方法(課目Ⅱの熱力学)
③勉強方法(課目Ⅱの流体・伝熱)
④勉強方法(課目Ⅲ・課目Ⅳ)
⑤勉強方法(課目Ⅰ)
⑥買った参考書
⑦2018年試験の変わった点
の7部構成になっています。
この記事は ②勉強方法(課目Ⅱの熱力学) です。
エネルギー管理士試験 「熱分野」 で
一番 難しいのが 課目Ⅱ でした
この 課目Ⅱ を 理解すれば、
あとは暗記が主流なので
ぜひとも理解しておきたいのですが、
専門外の人は 課目Ⅱの問題を見て、
試験そのものも諦めてしまうのではないでしょうか!?
私も この課目Ⅱを一番最初に取り組み、
そして、もっとも時間を掛けました。
課目Ⅱの問題は4問あり (問題4~7)
熱力学 で 2問 配点50%
流体工学 で 1問 配点25%
伝熱工学 で 1問 配点25% です
2017年までの傾向では 配点50%を占める熱力学が
がっつりとした 応用問題 の 計算問題 なので、
この熱力学を理解して、応用できるかどうかが
合格の分かれ目に なっているように思いました。
なので、
まず最初に課目Ⅱの熱力学をじっくりと1ヶ月間かけて取り組みました。
その時に使った参考書は


オーム社のエネルギー管理士試験(熱分野)徹底研究 です
出題範囲内の基礎的な教科書として使えながら、
練習問題に解説を分かりやすく書いています。
どちらかというと、練習問題の解説を読んではじめて
エネルギー管理士試験の内容を網羅しています
なので、勉強のできる人は
この本 と 過去問 を やれば合格できると思います。
ただ、
専門外の私には、ほんと~に理解できなかったので
結構早いうちに これも買ってみました


マンガでわかる熱力学(≧▽≦)
これを読んだからといって
エネルギー管理士試験には絶対合格しません ヾ(。>﹏<。)ノ゙✧*。
ただ、なにかボヤ~と理解できたような気になって
とっつきやすくなったのは事実でした (≧▽≦)
熱力学で行き詰った人は
一度読んでみるのもいいかもしれません。
私は読んで正解でした。
期間としては
3月の1ヶ月間は全て熱力学をやっていました。
そして、5月ごろから過去問題をやっています。
使った過去問題集は

2022年版 エネルギー管理士熱分野模範解答集
この過去問題集は
年代別では無くて、
課目別⇒年代別 に 分かれているので
おなじ課目を集中して勉強するのにすごく便利でした。
課目Ⅱの過去問は平成27年がとても良問で
やや易し目で、基本的な内容も網羅しているので
一番初めは平成27年からすることをお勧めします。
私は専門外だったので、
この過去問集を使って徹底的に
5年前までは3回、10年前までは2回 繰り返し解きました。
専門の人は 3~5年前までを2回解けばなんとかなるかもしれません。
ただそれでも計算問題が不安だった私は
計算問題用にこの本も買いました


やさしい熱計算演習
ただ、この計算問題集は
問題が古すぎるのと、私には難しすぎるところがあって
結局、1回だけ、さらっと解いただけで
そんなに重宝しませんでした。
試験1年目にはいらないかもしれませんが、
試験2年目以降で課目Ⅱを落とした人にはいいと思います。
さらに 忘れてはならないのが
試験問題を作っている省エネルギーセンターが書いてる参考書


エネルギー管理士試験講座 熱分野〈2〉熱と流体の流れの基礎
私は買いませんでしたが、
私の同僚はこちらを買って課目Ⅱを1年目で取っていました。
参考書には載っていない様な
こまかな内容も乗っていますので、
少しでも点数をアップさせたい試験2年目以降の人にお勧めします。
私なりに 熱力学 の 要点 を まとめてみると
①SI単位と組み立て単位
②水の三態と湿度
③理想気体の状態方程式
次の記事へ
専門外の私がエネルギー管理士を一発合格した体験記です
記事は①~⑦まであり、
①受験背景と試験概要
②勉強方法(課目Ⅱの熱力学)
③勉強方法(課目Ⅱの流体・伝熱)
④勉強方法(課目Ⅲ・課目Ⅳ)
⑤勉強方法(課目Ⅰ)
⑥買った参考書
⑦2018年試験の変わった点
の7部構成になっています。
この記事は ②勉強方法(課目Ⅱの熱力学) です。
1.課目Ⅱ 熱と流体の流れの基礎
エネルギー管理士試験 「熱分野」 で
一番 難しいのが 課目Ⅱ でした
この 課目Ⅱ を 理解すれば、
あとは暗記が主流なので
ぜひとも理解しておきたいのですが、
専門外の人は 課目Ⅱの問題を見て、
試験そのものも諦めてしまうのではないでしょうか!?
私も この課目Ⅱを一番最初に取り組み、
そして、もっとも時間を掛けました。
課目Ⅱの問題は4問あり (問題4~7)
熱力学 で 2問 配点50%
流体工学 で 1問 配点25%
伝熱工学 で 1問 配点25% です
2017年までの傾向では 配点50%を占める熱力学が
がっつりとした 応用問題 の 計算問題 なので、
この熱力学を理解して、応用できるかどうかが
合格の分かれ目に なっているように思いました。
なので、
まず最初に課目Ⅱの熱力学をじっくりと1ヶ月間かけて取り組みました。
2. 熱力学の勉強方法
その時に使った参考書は

オーム社のエネルギー管理士試験(熱分野)徹底研究 です
出題範囲内の基礎的な教科書として使えながら、
練習問題に解説を分かりやすく書いています。
どちらかというと、練習問題の解説を読んではじめて
エネルギー管理士試験の内容を網羅しています
なので、勉強のできる人は
この本 と 過去問 を やれば合格できると思います。
ただ、
専門外の私には、ほんと~に理解できなかったので
結構早いうちに これも買ってみました

マンガでわかる熱力学(≧▽≦)
これを読んだからといって
エネルギー管理士試験には絶対合格しません ヾ(。>﹏<。)ノ゙✧*。
ただ、なにかボヤ~と理解できたような気になって
とっつきやすくなったのは事実でした (≧▽≦)
熱力学で行き詰った人は
一度読んでみるのもいいかもしれません。
私は読んで正解でした。
期間としては
3月の1ヶ月間は全て熱力学をやっていました。
そして、5月ごろから過去問題をやっています。
使った過去問題集は

2022年版 エネルギー管理士熱分野模範解答集
この過去問題集は
年代別では無くて、
課目別⇒年代別 に 分かれているので
おなじ課目を集中して勉強するのにすごく便利でした。
課目Ⅱの過去問は平成27年がとても良問で
やや易し目で、基本的な内容も網羅しているので
一番初めは平成27年からすることをお勧めします。
私は専門外だったので、
この過去問集を使って徹底的に
5年前までは3回、10年前までは2回 繰り返し解きました。
専門の人は 3~5年前までを2回解けばなんとかなるかもしれません。
ただそれでも計算問題が不安だった私は
計算問題用にこの本も買いました

やさしい熱計算演習
ただ、この計算問題集は
問題が古すぎるのと、私には難しすぎるところがあって
結局、1回だけ、さらっと解いただけで
そんなに重宝しませんでした。
試験1年目にはいらないかもしれませんが、
試験2年目以降で課目Ⅱを落とした人にはいいと思います。
さらに 忘れてはならないのが
試験問題を作っている省エネルギーセンターが書いてる参考書

エネルギー管理士試験講座 熱分野〈2〉熱と流体の流れの基礎
私は買いませんでしたが、
私の同僚はこちらを買って課目Ⅱを1年目で取っていました。
参考書には載っていない様な
こまかな内容も乗っていますので、
少しでも点数をアップさせたい試験2年目以降の人にお勧めします。
3.熱力学の要点
私なりに 熱力学 の 要点 を まとめてみると
①SI単位と組み立て単位
②水の三態と湿度
③理想気体の状態方程式
④熱力学第一法則
⑤状態変化
・状態変化とポリトロープ指数
・状態変化とΔU・ΔQ・ΔH・ΔS・ΔW
⑥熱機関の状態変化と効率を覚える
⑦蒸気サイクル(ランキンサイクル)
⑧冷凍サイクル(逆ランキンサイクル)
「これを覚えればあと楽」 な内容が①~⑧だと思います。
(そりゃそうだ・・・って言われそうですが)
①と②はメチャ基礎的なことなんだと思いますが、
専門外の人は初めにここを抑えないとチンプンカンプンです。
あと、①の単位って意外に問題を解くヒントになっていて、
解き方が分からなくても、答えの単位になるように×や÷を考えていくと
解けることもあります。
③ PV=mRT
④ dU=dH+dW
⑤ 等温・等容・等圧・断熱
→ PV^κ=一定 (κはポリトロープ指数)
→ ΔU・ΔQ・ΔH・ΔS・ΔW
その中でも応用の③~⑧すべてに付きまとうのが ”⑤状態変化”
等温・等容・等圧・断熱 の内、
この問題はどの状態かを考えてから、
・状態変化とポリトロープ指数
・状態変化とΔU・ΔQ・ΔH・ΔS・ΔW
⑥熱機関の状態変化と効率を覚える
⑦蒸気サイクル(ランキンサイクル)
⑧冷凍サイクル(逆ランキンサイクル)
「これを覚えればあと楽」 な内容が①~⑧だと思います。
(そりゃそうだ・・・って言われそうですが)
①と②はメチャ基礎的なことなんだと思いますが、
専門外の人は初めにここを抑えないとチンプンカンプンです。
あと、①の単位って意外に問題を解くヒントになっていて、
解き方が分からなくても、答えの単位になるように×や÷を考えていくと
解けることもあります。
③ PV=mRT
④ dU=dH+dW
⑤ 等温・等容・等圧・断熱
→ PV^κ=一定 (κはポリトロープ指数)
→ ΔU・ΔQ・ΔH・ΔS・ΔW
その中でも応用の③~⑧すべてに付きまとうのが ”⑤状態変化”
等温・等容・等圧・断熱 の内、
この問題はどの状態かを考えてから、
どの公式に当てはめるのかをいつも考えていました。
特に③~⑤は
状態変化によって、最終の公式が変わるので
最初はまったく理解できませんでした。
(本来は公式で覚える世界じゃないんでしょうね~)
特に⑤のΔU・ΔQ・ΔH・ΔS・ΔWは
自分のノートに

と、いうような まとめ を作って、ひたすら暗記 しました
最初は
定容比熱Cv か 定圧比熱Cp の どちらを使うのかが
理解できずに困っていました。
今の覚え方は、
ΔU:内部エネルギーはいつも Cv
ΔQ:熱量 と ΔS:エントロピーは
等容ならCv 、等圧ならCp
と 覚えられると結構楽になりました。
等温と断熱の問題が曲者で、
難しい式の代入で 別の式を作るのが多いので
これはたくさん問題を解くのがいいかなと思います。
⑥熱機関は
カ・オ・デ・ブ・ス 顔・デブ・ブス・・・ラ!? と、覚えて
カ → カルノーサイクル
オ → オットーサイクル
デ → ディーゼルサイクル
ブ → ブレイトンサイクル
ス → スターリングサイクル
+ラ → ランキンサイクル
と、順番を丸覚えしたあと

T:等温、V:等容、P:等圧、D:断熱
と、いうのを繰り返し覚えていました。
⑦蒸気サイクル(ランキンサイクル)
⑧冷凍サイクル(逆ランキンサイクル)
は、
○サイクルと装置を覚える
○乾き度の計算方法
○飽和蒸気・飽和水のエントロピーやエンタルピーから
湿り蒸気のエントロピー・エンタルピーを求める
○効率
の方法さえ覚えれば、
比較的簡単に解けると思います。
課目Ⅱに関してだけは
1ヶ月間しっかり基礎を付けてから、過去問をやりだしました。
ちなみに
2018年は
・オットーサイクル
・蒸気サイクル
・冷凍サイクル
がメインの問題がでました。
例年より計算問題が少なく、
明らかに簡単な問題だったので
正直、こんなに勉強しなくても
解けていたと思いましたので、
その点はラッキーでしたね~。
もちろん、その次の
「流体工学」や「伝熱工学」も曲者なので
勉強は必要になります。
特に③~⑤は
状態変化によって、最終の公式が変わるので
最初はまったく理解できませんでした。
(本来は公式で覚える世界じゃないんでしょうね~)
特に⑤のΔU・ΔQ・ΔH・ΔS・ΔWは
自分のノートに

と、いうような まとめ を作って、ひたすら暗記 しました
最初は
定容比熱Cv か 定圧比熱Cp の どちらを使うのかが
理解できずに困っていました。
今の覚え方は、
ΔU:内部エネルギーはいつも Cv
ΔQ:熱量 と ΔS:エントロピーは
等容ならCv 、等圧ならCp
と 覚えられると結構楽になりました。
等温と断熱の問題が曲者で、
難しい式の代入で 別の式を作るのが多いので
これはたくさん問題を解くのがいいかなと思います。
⑥熱機関は
カ・オ・デ・ブ・ス 顔・デブ・ブス・・・ラ!? と、覚えて
カ → カルノーサイクル
オ → オットーサイクル
デ → ディーゼルサイクル
ブ → ブレイトンサイクル
ス → スターリングサイクル
+ラ → ランキンサイクル
と、順番を丸覚えしたあと

T:等温、V:等容、P:等圧、D:断熱
と、いうのを繰り返し覚えていました。
⑦蒸気サイクル(ランキンサイクル)
⑧冷凍サイクル(逆ランキンサイクル)
は、
○サイクルと装置を覚える
○乾き度の計算方法
○飽和蒸気・飽和水のエントロピーやエンタルピーから
湿り蒸気のエントロピー・エンタルピーを求める
○効率
の方法さえ覚えれば、
比較的簡単に解けると思います。
課目Ⅱに関してだけは
1ヶ月間しっかり基礎を付けてから、過去問をやりだしました。
ちなみに
2018年は
・オットーサイクル
・蒸気サイクル
・冷凍サイクル
がメインの問題がでました。
例年より計算問題が少なく、
明らかに簡単な問題だったので
正直、こんなに勉強しなくても
解けていたと思いましたので、
その点はラッキーでしたね~。
もちろん、その次の
「流体工学」や「伝熱工学」も曲者なので
勉強は必要になります。
次の記事へ
【エネルギー管理士】 合格証
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ⑦2018年試験の変わった点
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ⑥買った参考書
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ⑤勉強方法(課目Ⅰ)
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ④勉強方法(課目Ⅲ・課目Ⅳ)
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ③勉強方法(課目Ⅱの流体・伝熱)
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ⑦2018年試験の変わった点
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ⑥買った参考書
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ⑤勉強方法(課目Ⅰ)
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ④勉強方法(課目Ⅲ・課目Ⅳ)
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ③勉強方法(課目Ⅱの流体・伝熱)