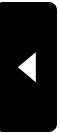【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ⑦2018年試験の変わった点
2018年08月18日
これらの記事は
専門外の私がエネルギー管理士を一発合格した体験記です
記事は①~⑦まであり、
①受験背景と試験概要
②勉強方法(課目Ⅱの熱力学)
③勉強方法(課目Ⅱの流体・伝熱)
④勉強方法(課目Ⅲ・課目Ⅳ)
⑤勉強方法(課目Ⅰ)
⑥買った参考書
⑦2018年試験の変わった点
の7部構成になっています。
この記事は ⑦2018年試験の変わった点 です。
2018年のエネルギー管理士試験(熱分野)を受けて
出題と傾向が ガラッ って変わったな~
変えようとしているのかな~
と、思いました。
以下、過去5年以上と比べて
2018年の変わった点を紹介したいと思います。
試験を受けなくても変わったと分かる点として
①一日の試験を受ける順番が変わった
②課目Ⅳの満点が20点上がった
が、あります。
2018年から 試験の順番が変わっていて
課目Ⅲ→Ⅳ→Ⅱ→Ⅰ から Ⅰ→Ⅱ→Ⅳ→Ⅲ
に変更になっています。
これは一目でわかる、大きな変更でした。
というのも、以前の順番は
2018年対照の参考書にも載っている内容なので
長年続いた「変わらないもの・・・」という認識だったんでしょうね~
また、課目Ⅳ「熱利用設備およびその管理」は
今まで260点満点だったのが
280満点に変わっています。
これは選択問題2題の配点が
それぞれ30点から40点に変わっていて、
選択問題の割合が増えていました。
最終的には
● 9:00~10:20( 80分)
課目Ⅰ 「エネルギー総合管理及び法規」200点満点
○休憩 30分
●10:50~12:40(110分)
課目Ⅱ 「熱と流体の流れの基礎」 200点満点
○休憩 100分
●14:00~15:50(110分)
課目Ⅳ 「熱利用設備およびその管理」 280点満点
○休憩 30分
●16:20~17:40( 80分)
課目Ⅲ 「燃料と燃焼」 110点満点
と、なっています。
これは感覚でしかないのですが、
難易度が変わったように感じました。
2018年は
○難問だった 課目Ⅱの熱力学が 超簡単
流体や伝熱の方が難しかった。
○課目Ⅲ・Ⅳでは
参考書に載っていない様な内容が多かった。
難しくなり、これからどう勉強するべきか・・・
と思いました。
結果として・・・・
超難問の課目Ⅱが優しくなったので
総合的には 易しくなった と 感じました。
課目Ⅰ 「エネルギー総合管理及び法規」
課目Ⅰは例年通りという感じでした。
課目Ⅱ 「熱と流体の流れの基礎」
上でも述べましたが、
一番の難所である熱力学が超簡単でした。
出題されたのが
・オットーサイクル(50点)
・ランキンサイクル(21点)
・逆ランキンサイクル(39点)
特に、ランキン・逆ランキンの問題は
計算問題がまったく無かったです。
このサイクルの基礎を知っていれば
50点満点とれるのではないかという問題でした。
その代わり伝熱工学や例年より少し難しくなっていました
ただ、私が「捨てよう」と決めた「円管の伝熱」だったので
そう感じただけかもしれません。
それを捨てても、他が簡単なので
課目Ⅱとしては 問題ないと思います。
課目Ⅲ 「燃料と燃焼」
課目Ⅲは 少しだけ難しくなっていて
問題8では
ややマニアックな液体燃料の粒径の問題がでました。
問題9は
ちょっとややこしい
『6つのうち、間違っているものを2つ答えよ』が2つありましたが、
問題9の全部がその問題というわけではなかったです。
問題10 燃焼計算 は
人によっては超難問だったかもしれません。
珍しい出題形式で
①プロパンとブタンの混合燃料
②そして モル分率 を 問われる・・・・
モル分率 が分からなくて止まった人が多くいたようでした。
モル分率 は いちお高校化学でも出てくるんですが、
物理・機械専攻の人はなじみがないと思います。
過去問にもでていなくて、
さらに 省エネルギーセンターの試験講座(本)にも出ていませんでした(笑)
課目Ⅳ 「熱利用設備およびその管理」
私は課目Ⅳだけ、受かった実感が湧かず、
どちらかといえば、「落ちたかも・・・」と思いました
と、いうのも、
やったことがない問題が非常に多かったからです。
一番初めの問題11でいきなり
誤差について・・・・ ( ̄▽ ̄;)
その次は 定番 の 熱電対温度計 だったんですが、
過去問では熱電対温度計はよくでていて
しっかり勉強していました! o( ̄ー ̄)○
定番のキーワードである
ゼ―ベック効果・熱起電力・補償導線
エクステンション形・コンペンセーション型
熱電対の種類や温度範囲 などなど
ドンと来い!という問題でしたが!
・・・・そんなキーワード1つもでてきません(T ^ T)
問題読みながらプチ混乱していました
でてきた問題は
・熱電対の保護管の長さ・・・
・測定誤差になる要因・・・
・測り方の工夫・・・・
・・・みんな知りません <(T◇T)>!!!
さらに次の問題で追い打ちがあって、
問題11は 温度計・流量計の問題が主流なのですが、
・・・・圧力計 って・・・・・・ ヾ(。>﹏<。)ノ゙✧* マッタクシリマセン
出題範囲が広いこともありますが、
ガラッ と 変わった印象でした
問題12 の 制御は
通常の問題で ここをしっかりとらないとヤバイ感じでした。
問題13・14も
どちらかといえば、実務経験に基づいた問題 が多いと思いました。
しかも 途中で 『熱力学?』って思うようなエントロピー計算が
ガッツリ入っています
課目Ⅳは 全体として
教科書を読んでも答え辛い問題が多いと思いました。
終わった直後は自信が無かったのですが、
とりあえず合格してほんと良かったです
2018年の試験問題の総評として、
もしかして 合格率を上げようとしているのでは? と
感じました
超難問の熱力学を簡単にして、門扉を広げ
実務経験を頑張っていれば答えられる問題を多くする・・・・
(それでも、ちょっと専門が変わるとチンプンカンプンですが)
と、いう風に感じました。
この2018年の傾向が来年も続くかどうかわからないので
2019年の受験者は例年通りの勉強をするのが得策だと思いますが、
2~3年かけて合格してもいい人は
勉強を 浅く広く で 軽くやって
2年後以降は 少なくなった勉強範囲をガッツリやる・・・
という方法でも、そこそこの合格率がでるように思います。
以上が
専門外の私が無茶ブリで挑戦した
エネルギー管理士の記録です。
なにかの参考になれば 幸いです
専門外の私がエネルギー管理士を一発合格した体験記です
記事は①~⑦まであり、
①受験背景と試験概要
②勉強方法(課目Ⅱの熱力学)
③勉強方法(課目Ⅱの流体・伝熱)
④勉強方法(課目Ⅲ・課目Ⅳ)
⑤勉強方法(課目Ⅰ)
⑥買った参考書
⑦2018年試験の変わった点
の7部構成になっています。
この記事は ⑦2018年試験の変わった点 です。
2018年のエネルギー管理士試験(熱分野)を受けて
出題と傾向が ガラッ って変わったな~
変えようとしているのかな~
と、思いました。
以下、過去5年以上と比べて
2018年の変わった点を紹介したいと思います。
1.公式に変わった点
試験を受けなくても変わったと分かる点として
①一日の試験を受ける順番が変わった
②課目Ⅳの満点が20点上がった
が、あります。
2018年から 試験の順番が変わっていて
課目Ⅲ→Ⅳ→Ⅱ→Ⅰ から Ⅰ→Ⅱ→Ⅳ→Ⅲ
に変更になっています。
これは一目でわかる、大きな変更でした。
というのも、以前の順番は
2018年対照の参考書にも載っている内容なので
長年続いた「変わらないもの・・・」という認識だったんでしょうね~
また、課目Ⅳ「熱利用設備およびその管理」は
今まで260点満点だったのが
280満点に変わっています。
これは選択問題2題の配点が
それぞれ30点から40点に変わっていて、
選択問題の割合が増えていました。
最終的には
● 9:00~10:20( 80分)
課目Ⅰ 「エネルギー総合管理及び法規」200点満点
○休憩 30分
●10:50~12:40(110分)
課目Ⅱ 「熱と流体の流れの基礎」 200点満点
○休憩 100分
●14:00~15:50(110分)
課目Ⅳ 「熱利用設備およびその管理」 280点満点
○休憩 30分
●16:20~17:40( 80分)
課目Ⅲ 「燃料と燃焼」 110点満点
と、なっています。
2.問題の難易度が変わった?
これは感覚でしかないのですが、
難易度が変わったように感じました。
2018年は
○難問だった 課目Ⅱの熱力学が 超簡単
流体や伝熱の方が難しかった。
○課目Ⅲ・Ⅳでは
参考書に載っていない様な内容が多かった。
難しくなり、これからどう勉強するべきか・・・
と思いました。
結果として・・・・
超難問の課目Ⅱが優しくなったので
総合的には 易しくなった と 感じました。
3.各課目の変わったと思う点
課目Ⅰ 「エネルギー総合管理及び法規」
課目Ⅰは例年通りという感じでした。
課目Ⅱ 「熱と流体の流れの基礎」
上でも述べましたが、
一番の難所である熱力学が超簡単でした。
出題されたのが
・オットーサイクル(50点)
・ランキンサイクル(21点)
・逆ランキンサイクル(39点)
特に、ランキン・逆ランキンの問題は
計算問題がまったく無かったです。
このサイクルの基礎を知っていれば
50点満点とれるのではないかという問題でした。
その代わり伝熱工学や例年より少し難しくなっていました
ただ、私が「捨てよう」と決めた「円管の伝熱」だったので
そう感じただけかもしれません。
それを捨てても、他が簡単なので
課目Ⅱとしては 問題ないと思います。
課目Ⅲ 「燃料と燃焼」
課目Ⅲは 少しだけ難しくなっていて
問題8では
ややマニアックな液体燃料の粒径の問題がでました。
問題9は
ちょっとややこしい
『6つのうち、間違っているものを2つ答えよ』が2つありましたが、
問題9の全部がその問題というわけではなかったです。
問題10 燃焼計算 は
人によっては超難問だったかもしれません。
珍しい出題形式で
①プロパンとブタンの混合燃料
②そして モル分率 を 問われる・・・・
モル分率 が分からなくて止まった人が多くいたようでした。
モル分率 は いちお高校化学でも出てくるんですが、
物理・機械専攻の人はなじみがないと思います。
過去問にもでていなくて、
さらに 省エネルギーセンターの試験講座(本)にも出ていませんでした(笑)
課目Ⅳ 「熱利用設備およびその管理」
私は課目Ⅳだけ、受かった実感が湧かず、
どちらかといえば、「落ちたかも・・・」と思いました
と、いうのも、
やったことがない問題が非常に多かったからです。
一番初めの問題11でいきなり
誤差について・・・・ ( ̄▽ ̄;)
その次は 定番 の 熱電対温度計 だったんですが、
過去問では熱電対温度計はよくでていて
しっかり勉強していました! o( ̄ー ̄)○
定番のキーワードである
ゼ―ベック効果・熱起電力・補償導線
エクステンション形・コンペンセーション型
熱電対の種類や温度範囲 などなど
ドンと来い!という問題でしたが!
・・・・そんなキーワード1つもでてきません(T ^ T)
問題読みながらプチ混乱していました
でてきた問題は
・熱電対の保護管の長さ・・・
・測定誤差になる要因・・・
・測り方の工夫・・・・
・・・みんな知りません <(T◇T)>!!!
さらに次の問題で追い打ちがあって、
問題11は 温度計・流量計の問題が主流なのですが、
・・・・圧力計 って・・・・・・ ヾ(。>﹏<。)ノ゙✧* マッタクシリマセン
出題範囲が広いこともありますが、
ガラッ と 変わった印象でした
問題12 の 制御は
通常の問題で ここをしっかりとらないとヤバイ感じでした。
問題13・14も
どちらかといえば、実務経験に基づいた問題 が多いと思いました。
しかも 途中で 『熱力学?』って思うようなエントロピー計算が
ガッツリ入っています
課目Ⅳは 全体として
教科書を読んでも答え辛い問題が多いと思いました。
終わった直後は自信が無かったのですが、
とりあえず合格してほんと良かったです
2018年の試験問題の総評として、
もしかして 合格率を上げようとしているのでは? と
感じました
超難問の熱力学を簡単にして、門扉を広げ
実務経験を頑張っていれば答えられる問題を多くする・・・・
(それでも、ちょっと専門が変わるとチンプンカンプンですが)
と、いう風に感じました。
この2018年の傾向が来年も続くかどうかわからないので
2019年の受験者は例年通りの勉強をするのが得策だと思いますが、
2~3年かけて合格してもいい人は
勉強を 浅く広く で 軽くやって
2年後以降は 少なくなった勉強範囲をガッツリやる・・・
という方法でも、そこそこの合格率がでるように思います。
以上が
専門外の私が無茶ブリで挑戦した
エネルギー管理士の記録です。
なにかの参考になれば 幸いです
【エネルギー管理士】 合格証
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ⑥買った参考書
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ⑤勉強方法(課目Ⅰ)
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ④勉強方法(課目Ⅲ・課目Ⅳ)
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ③勉強方法(課目Ⅱの流体・伝熱)
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ②勉強方法(課目Ⅱの熱力学)
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ⑥買った参考書
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ⑤勉強方法(課目Ⅰ)
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ④勉強方法(課目Ⅲ・課目Ⅳ)
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ③勉強方法(課目Ⅱの流体・伝熱)
【エネルギー管理士 一発合格体験記】 ②勉強方法(課目Ⅱの熱力学)